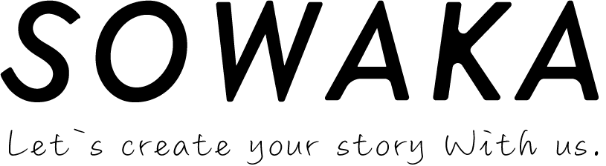【瀬戸市】Y・Y様邸 クラックを防ぐための“ひと手間”。廊下のコンクリート工事
築28年のダイワハウスのリノベーション。
「廊下のフローリングを、どうしてもコンクリート仕上げにしたい」そんなY様の想いを受けて、コンクリート金鏝(かなごて)仕上げで施工を進めています。

通常、木下地の上にコンクリートを流し込むことはありません。コンクリートに含まれる水分を木下地が吸ってしまうと、木が反ったり歪んだりする原因となり、結果として仕上がったコンクリートにクラック(ひび割れ)が入りやすくなるためです。
そこで今回は、木下地の上に直接コンクリートを流さないように防水シートを敷いて、下地に水分が浸透しないようにしました。木とコンクリートが直接触れないように、防水シートで“仕切り”を設け、下地への影響を抑えて、できる限りクラックの発生を抑える工夫をしました。ドキドキ!!


コンクリートを流し込む範囲には、まずコンパネなどを使って型枠をしっかり組みます。そのうえで、床全体に鉄筋やワイヤーメッシュを配置し、コンクリートに必要な強度を確保します。
また、施工範囲が広い場合は伸縮目地を入れることで、温度変化や乾燥収縮によるひび割れを抑え、耐久性を高める工夫を行います。

廊下から続くトイレも同じように施工を進めていきます。

写真は、まだ型枠を本締めする前の段階ですが、型枠をしっかり固定したら、左官屋さんが練り上げたコンクリートを少しずつ流し込みながら、全体を均していきます。
写真には写っていませんが、左官屋さんは練ったコンクリートを手で何度も運び、廊下全体へ丁寧に流し込む作業を繰り返しています。こうした細かな積み重ねが、仕上がりの美しさにつながります。
廊下一面がコンクリート金鏝で滑らかに整い、美しい表情が現れる瞬間がとても楽しみです。

コンクリートが完全に乾くまでには、2~3日ほどの養生期間が必要です。
この間は、仕上がりを守るために他の職人さんの立ち入りは一切禁止となります。
わずかな振動や荷重でも表面に跡がついたり、仕上がりが不均一になってしまうため、しっかりと乾かすことが、とても大切な工程です。


養生期間が終わり、しっかり乾いた状態の写真です。
仕上げた直後はコンクリートが濃い色をしていますが、乾くにつれてやわらかなグレーへと落ち着いていきます。
金鏝仕上げも、左官職人さんの丁寧な手仕事が光っており、表面のツヤや均一さがとても美しく仕上がっています。
そして今のところ、クラックも入らず、とても良い状態。よかった(ホッ・・・)

お客様にも現場にお越しいただき、実際の仕上がりを直接ご確認いただきました。念願だったコンクリートの床にとても喜んでくださり、こちらも思わずホッとした瞬間でした。
土間コンクリートの仕上げは、ほかの床仕上げに比べて大がかりな工程が必要になります。しかし、その手間以上に、空間の表情や質感に大きな価値をもたらす仕上げです。
店舗づくりで個性を出したい方、オフィスにアクセントを取り入れたい方、そして住まいに“少し特別な雰囲気”を取り入れたい方にも、土間コンクリートは相性抜群。
床をコンクリート仕上げにすることで、空間は驚くほど変わります。ぜひ一度、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
(現場からの一言)施工はめちゃくちゃ大変です・・・笑

この記事を書いた人

坂本真由
坂本真由(株式会社SOWAKA)
代表取締役
1984年、熊本県天草市生まれ。
田舎ならではの独特な世界観や価値観に刺激を受けながら育ち、「自分らしく生きる」という人生のテーマを教えてくれた、大好きな地元が私の原点です。
そんな地元を離れたのは、「建築とデザイン」を本格的に学びたかったから。新しい刺激を求めて飛び込んだ専門学校では、建築の基礎から空間づくり、そしてデザインの楽しさを2年間夢中になって学びました。
卒業後は名古屋のビルダーに就職し、現場での経験を重ねながら、より実践的な建築の世界を体感。地元で培った感性と、愛知での学びや経験が、今の私の仕事にしっかりと息づいています。